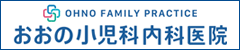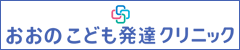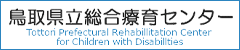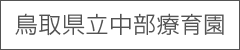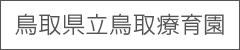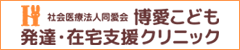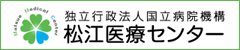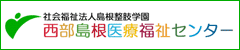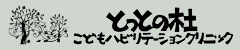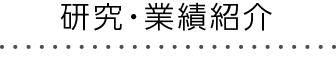
- 脳神経小児科の研究・業績を紹介いたします。
- ウエスト症候群の脳波解析による予後予測
- ウエスト症候群は乳児期に発症する薬剤抵抗性てんかんの1つで、脳MRI以外に予後を予測するツールが乏しいことが問題である。早期に予後を予測することができれば、患者さん毎にオーダーメイドの治療方針を立てることが可能となる。そこで当科では、発症時の脳波検査をコンピューター解析することで、客観的に予後を予測することを目的とした研究を行い、原著論文など多くの業績をあげている。
- ライソゾーム病に対する薬理学的シャペロン療法の開発
- ライソゾーム病は先天的な酵素欠損により生じる神経変性疾患である。現在、神経症状に有効な治療法は極めて乏しく、開発が望まれている。我々は脳内に移行可能な基質類似体(シャペロン化合物)を用いて、神経型ゴーシェ病に対する基礎ならびに臨床研究を実施している。この研究により、神経変性疾患の中枢神経治療法の確立の早期実現を目指している。
- 医療的ケア児の災害対策
- 鳥取県内には約130名の医療的ケア児が在宅での生活をしている。東日本大震災や熊本大地震、西日本豪雨といった規模の災害が当県でもいつ起こるかわからず、対策は喫緊の課題である。当科は当院の高度救急救命センターや鳥取県と協力し、医療的ケア児が避難できる福祉避難所の設立・運営を行うための手法を検討し、地域とともに災害対策を行なっている。
- 急性脳症の疫学と早期診断法
- 急性脳症は、小児の後天性脳障害の主要なものである。本邦に多いがその正確な発生頻度や病型、予後などは知られていない。鳥取県の急性脳症の疫学研究を行い、臨床症状や臨床検査所見から早期診断に有用な因子を抽出する研究を行っている。
- 急性脳症の脳波解析による早期診断
- 急性脳症に特異的な検査はMRIであるが、発症から数日は異常を認めないことがしばしばである。そこで、発症初期から高率に異常所見を認める脳波検査を利用して、急性脳症の診断に有用な脳波所見を見出すために、視覚的ならびにコンピューター解析で研究を行っている。この研究により、熱性けいれんと急性脳症を判別できる新しい方法を開発することを目指している。
- 医療的ケアの必要な障害児の在宅支援チームの確立
- 近年、新生児医療の進歩、救急医療の進歩により、以前は救命できなかった命が助かるようになってきた。しかし、命は助かっても障害を残してしまうケースは少なくない。その中には、気管切開、人工呼吸、胃瘻栄養、吸引などの医療的ケアを必要として自宅へ退院するケースも多い。医療的支援だけでなく、生活を見越した支援を行うために、医療と福祉が協力し支援できる地域の体制を確立できるよう努めている。