鳥取大学医学部では、前身となる米子医学専門学校開学(1945年)以来今日まで、
一度も滞ることなく、医学生・医師の育成に取り組ませていただいています。
これもひとえに地域の皆様の献体への深いご理解とご協力の賜物であります。
鳥取大学関係者一同、深くお礼申し上げます。
医学教育・医療安全のために
引き続き、献体への
ご協力をお願いします。
お問い合わせ
鳥取大学米子地区事務部学務課学生係・献体担当
0859-38-7100
me-gakusei●ml.adm.tottori-u.ac.jp
メールの場合は、上記アドレスの●を@に書き換えてください。
ご関心をお持ちいただけましたら、「献体のしおり」をご覧ください。
ボタンをクリックするとダウンロードできます。
または、問い合わせ窓口(鳥取大学米子地区事務部学務課学生係・献体担当)にご連絡いただければ「献体のしおり」を郵送させていただきます。
献体に関する情報
献体とは
献体とは、死後にみずからの身体を医学・歯学の教育のために大学で行われる正常解剖(身体の正常な構造を理解するための解剖学実習)に提供する行為、または、提供したご遺体を言います(参考:医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 第1,2条)。
献体の理念は、医の倫理に立脚した良医の育成を目的とし、無条件・無報酬のもと、みずからの意思でご自身の遺体を提供することとされています。このため、生前にご本人様のお申し出による献体登録が必要です。
医学生は、ご献体の解剖を通して医学的な知識を学び取るだけではなく、お身体をご提供してくださった方々の崇高な志や肉親の情を越えてご献体にご理解くださったご家族の思いを胸に深く刻み、「人間性」や「倫理性」をなお一層高めて参ります。
献体のもとでの取り組み
開学以来今日まで、医師を目指す医学生が、医学の基本として人体の正常構造を理解するためにご献体を解剖させていただいています(医学教育)。近年では、すでに医師となって治療にあたっている臨床医が手術の安全性の向上のために、ご献体で研修をさせていただき、医師となった後もご献体から学び続けることで、安全な医療を提供できる優れた医師を育成しています(臨床解剖教育)。さらに、より安全で患者への負担の小さい新しい手術法や手術機器の開発にもご献体で研修をさせていただく予定です(医療技術開発)。
鳥取大学は、皆様のご献体への深いご理解とご協力のもと、医学教育、臨床解剖教育、医療技術開発に取り組むことで、明日の医療を担う優れた医師の育成と安心を届ける新たな医療技術の開発を目指しています。
献体後のご遺体について
献体登録をされている方がお亡くなりになり、ご遺体を大学にお迎えすると、薬剤を用いて速やかに保存処置を行います。本学では、医学教育、臨床解剖教育および医療技術開発のそれぞれに適した方法で充分な保存処置がなされた後、一体ずつ保管庫に納め、解剖までの間、保管させていただきます。なお、臨床解剖教育および医療技術開発に使用するご遺体は冷凍保存させていただく場合もございます。
いずれの場合であっても、ご献体くださったご本人様に最大の敬意をはらいつつ対応させていただいています。解剖後のご遺体は、鳥取大学が責任をもって火葬させていただきます。
献体登録について
献体を行っていただくためには、ご本人様の意思で生前に「献体登録」を行っていただく必要があります。献体登録に必要な様式(献体の申込書等)をはじめ献体に関する詳細な情報は「献体のしおり」に記載されています。
なお、献体登録を行っていただく際には、ご家族の同意が必要です。
献体に関する本学の取り組み等をお知りになりたい場合は、本ウェブサイトの記載事項をご覧ください。不明な点がございましたら、遠慮なく次の問い合わせ先にご連絡ください。
鳥取大学米子地区事務部学務課学生係・献体担当(0859-38-7100)
医学教育
医学生の学びと
研究のために
教授 海藤 俊行
日頃より、鳥取大学医学部の解剖学教育にご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
医師は、患者さんの命を守るため、日々医療の現場で力を尽くしております。その診療の基盤となるのが、人体の構造に関する正確な知識です。このため、人体解剖学の修得は、医師を育成するうえで欠かすことのできない、大切な学びとなっております。
人体は、どのような精密機械でも再現できないほど複雑で精巧にできており、その理解には書籍やデジタル教材なども有用ではありますが、実際にご献体を通じて行う解剖学実習で得られる学びには、到底及びません。
現代の医療技術は目覚ましい発展を遂げていますが、がん、心疾患、脳血管疾患など、いまだ克服すべき病は数多く存在します。さらに、手術支援ロボットをはじめとする高度な医療を、安全かつ的確に行うためにも、より深い人体解剖の知識が求められております。
鳥取大学医学部では、解剖学教員の指導のもと、2年次に医学生が解剖学実習に取り組んでおります。その後も、学修の振り返りや臨床解剖教育、基礎医学研究などを通じて、ご献体を解剖する機会をいただいております。こうした学びの機会は、医学知識の修得にとどまらず、命の尊さや医の倫理を心に刻む、かけがえのない経験となっております。
鳥取大学医学部における医師の育成は、献体してくださった方々、そしてご家族・ご親族のご理解とご厚意なくしては成り立ちません。おかげさまで、医学部創設以来、解剖学教育を滞りなく継続することができておりますことを、あらためて深く感謝申し上げます。
今後とも、解剖学実習をはじめとする鳥取大学医学部の医学教育の重要性をご理解のうえ、献体事業へのご賛同とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
臨床解剖教育
優れた臨床医育成のために
センター長 黒﨑 雅道
医学生は、解剖学実習を通して人体の構造のみならず、医師としての確固とした倫理観、職業意識を学びます。また、医師となり手術を行う際にも人体の詳細な構造を正確に把握しておくことは大切であり、初めて手術を行う若手医師のみならず、高難度の手術を行う医師は、クリニカル・アナトミー・ラボと呼ばれる施設でご献体を用いた手術手技研修(臨床解剖教育)を行う必要があります。
多くの神経や血管が密集している頭蓋底部の外科的治療は高難度であり、その手術術式は日進月歩です。2001年11月にアメリカ合衆国デューク大学にて、「神の手をもつ」脳神経外科医として高名であった故福島孝徳教授のもとで手術手技研修を受ける機会を得ました。この研修こそが脳神経外科領域の微小解剖や手術術式を学ぶ最良の方法であるという考えに至り、私の脳神経外科医人生の大きな転機となりました。
クリニカル・アナトミー・ラボは、以前は、海外あるいは国内の限られた大学にしかありませんでしたが、ここ鳥取大学において、医療技術の向上、医療安全の推進、医学研究の発展、医療機器の研究開発などを目的として、2019年3月に「臨床解剖教育研修センター」という名称で設置されました。同年11月から研修が始まり、最大限の礼意を持ってご献体に向き合い、ご献体から学ばせていただくという姿勢のもと、現在までに、脳神経外科をはじめ、耳鼻咽喉・頭頸部外科、整形外科、泌尿器科、消化器外科、女性診療科などの多くの診療科が当センターにおいて手術手技研修を行っております。本センターは、山陰地域の医師を中心とした研修に加え、全国トップレベルの技術を持つ医師を講師に招いた研修も実施しています。一方で、本院医師が講師となり、全国各地の医師に優れた技術を提供することで、山陰地域にとどまらず全国の医療を支える取り組みも行っています。将来的には医療の発展を切望する海外の医師の技術支援も展開していきたいと考えています。
私どもは、ご献体を用いた研修を通して、患者さんに最良の医療をお届けすることができるよう日々精進しております。これもひとえに、献体していただいた皆様のご遺志とご遺族の深いご理解によるものと心より感謝申し上げるとともに、今後も臨床解剖教育のための献体についてご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
医療技術開発
新たな医療機器・手術手技の開発のために
センター長 藤原 和典
鳥取大学医学部附属病院では、「地域と歩む高度医療の実践」を理念とし、医学部全体が一体となって質の高い医療の提供に取り組んでいます。2011年には、全国に先駆けて低侵襲外科センターを設立し、安全なロボット支援手術の実践および全国への普及活動に注力してきました。また、2017年には新規医療推進センターを設立し、治験や臨床研究、医薬品や医療機器の開発支援体制を整備しました。さらに、2024年には附属病院に鳥取大学ロボット手術研修開発センターを開設し、低侵襲外科センターと協力して若手医師の教育を強化するとともに、患者さんの負担を軽減し術後の生活を快適にする新たな術式の開発を目指しています。また、新規医療推進センターと連携し、病院職員が日常診療で感じる「こんな医療機器があれば」という発想から新しい医療機器を開発し、患者さんにとって有益となる取り組みを山陰地区から広く発信していきます。
献体していただいたお身体の解剖は大変心苦しい行為でありますが、新しい術式や高度な医療機器の開発において、ご遺体を解剖させていただくことで新たな発見や実現可能性の判断ができるようになります。ご献体を用いた医療技術開発を行える施設は国内ではまだ限られていますが、徐々に増加傾向にあります。実際には、シミュレーション等で十分検証し、開発した機器や技術であっても、臨床の場で初めて試みることは安全性からも難しく、ご献体による検証がなければ技術開発が進まないことも多々あります。私たちの取り組みは、将来、手術現場などで活用され、患者さんの生命と健康を守ることに繋がります。医療技術や医療機器の開発は医師の育成と同様に欠かすことのできない取り組みです。こうした趣旨にご賛同いただき、献体についてご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
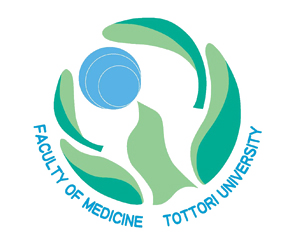 献体のご案内・鳥取大学
献体のご案内・鳥取大学