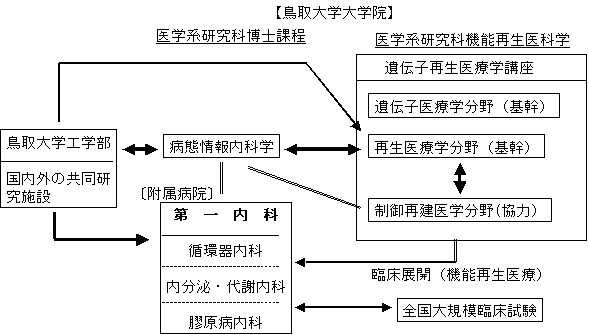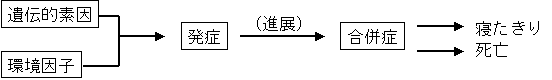鳥取大学医学部
■病態情報内科学分野■
Division of Molecular Medicine and Therapeutics
●病態情報内科学分野
分野名病態情報内科学分野 Division of Molecular Medicine and Therapeutics病態情報内科学個別ページ はこちらをご覧ください第一内科診療科群(循環器内科・内分泌代謝内科)(医学部附属病院HP内)電話番号TEL:0859-38-6517 FAX: 0859-38-6519スタッフの職名と氏名教授重政千秋 sigemasa@grape.med.tottori-u.ac.jp">sigemasa@grape.med.tottori-u.ac.jp(鳥取大学大学院医学系研究科 機能再生医科学専攻 遺伝子再生医療学講座 制御再建医学分野教授と兼担)准教授井川修 oigawa@grape.med.tottori-u.ac.jp">oigawa@grape.med.tottori-u.ac.jp(鳥取大学大学院医学系研究科 機能再生医科学専攻 遺伝子再生医療学講座 制御再建医学分野助教授と兼担)荻野和秀講師谷口晋一足立正光(医学部附属病院第一内科)助手濱田紀宏(医学部附属病院第一内科・学内講師)加藤雅彦(医学部附属病院第一内科・学内講師)矢野暁生(医学部附属病院第一内科)三明淳一朗(鳥取大学大学院医学系研究科 機能再生医科学専攻 遺伝子再生医療学講座 制御再建医学分野助手と兼担)鳥取大学大学院医学系研究科 機能再生医科学専攻 遺伝子再生医療学講座 再生医療学分野教授久留一郎助手山本康孝分野の特色病態情報内科学分野は内科学第一講座を前身としています。昭和20年9月28日に初代浅越嘉威教授の発令によって開講され、2005年(平成18年)が開講60周年に当たります。この間、第2代平田幸正教授、第3代真柴裕人教授によって担当され、学内において、主として循環器病学、内分泌代謝学、膠原病学(免疫学)の教育・研究・診療を担当する教室として発展してきました。
本分野は、医学部附属病院においては、第一内科として、循環器内科、内分泌代謝内科、膠原病内科を担当しています。平成8年厚生労働省は従来の「成人病」の一次予防を目的として、「生活習慣病」の名称を提唱し、新たな取り組みを開始していますが、第一内科の循環器内科、内分泌代謝内科の研究・診療の大きな部分を狭義の生活習慣病である動脈硬化症とその危険因子である糖尿病、高血圧、高脂血症、高尿酸血症、肥満症、メタボリックシンドローム、そしてその結果として発症する虚血性心疾患、心不全、不整脈等が占めています。
平成15年4月に鳥取大学大学院医学系研究科に「機能再生医科学」専攻が設置され、本分野の教授、助教授、助手1名が「遺伝子再生医療学」講座の協力分野である「制御再建医学」に所属し、医学部ならびに附属病院の従来の業務の全てを兼担しています。この「制御再建医学」分野は「再生医療学」分野と密接な協力体制を敷いています。分野での主要な研究テーマとその取り組みについての説明研究体制について
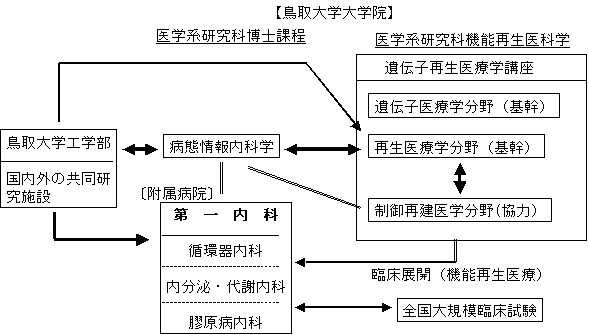
図示しましたように「病態情報内科学」分野の研究体制は以下の通り実施しています。
病態情報内科学と附属病院第一内科での研究体制
A、循環器研究グループ
B、内分泌代謝(免疫を含む)研究グループ
「機能再生医科学」専攻との連携
機能再生医科学専攻遺伝子再生医療学講座再生医療学分野(久留一郎教授)との密接な連携のもとに共同研究を行い、附属病院第一内科において臨床展開をめざします。 医工学連携研究の推進
鳥取大学工学部との共同研究を展開しています。 国内外の研究施設との共同研究の推進
教室員の海外、国内留学を推奨しています。これまで国内外の多くの研究施設との間で共同研究を実施してきました。 研究テーマとその取り組み 病態情報内科学と附属病院第一内科における研究テーマ 生活習慣病予防から血管再生医療展開をめざして
第一内科の診療分野の大きな部分を狭義の生活習慣病である動脈硬化症とその危険因子である糖尿病、高血圧、高脂血症、高尿酸血症、肥満症、メタボリックシンドローム、そしてその結果として発症する虚血性心疾患、不整脈、心不全が占めています。
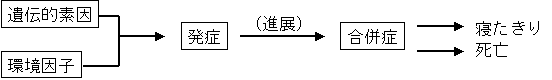
a. 発症・進展の予防
・遺伝子異常を含めた遺伝的素因からのアプローチ
・遺伝子多型解析による薬物効果判定
・EBMに基づく薬物治療法の開発(倫理委員会で承認された全国大規模臨床試験への参画)
・隠岐海士町住民健診(糖尿病を中心とした)参画をベースとした疫学調査研究
・内分泌代謝内科にコメディカル部門とのチーム医療に基づく「生活習慣病予防外来」を設置し、それを介した新たな予防法開発
b. 合併症に対する新たな治療法展開をめざして
・運動負荷試験を介した病態の解明
・運動リハビリテーションを介した虚血性心疾患ならびに閉塞性動脈硬化症(ASO)に対する血管再生治療応用
・既存ないし新規薬物を用いた細胞機能再生
・循環器内科に「動脈硬化・血管再生外来」を設置し、自己骨髄単核細胞移植によるASOや虚血性心疾患に対する血管再生医療 循環器研究グループにおける研究テーマ
(1)で述べた以外に下記研究を実施しています
a. 心血管系疾患の発症・進展のメカニズムならびに病態解明に関する内分泌代謝学的、免疫学的、電気生理学的ならびに分子生物学的研究
・心肥大機序
・血管平滑筋増殖機序
・心筋虚血耐性とミトコンドリアの役割
・アンジオテンシンIIと心房性不整脈
・心筋興奮とアデノシン効果
・その他
b. ランゲンドルフ潅流心を用いた研究
・既存の各種薬剤の心臓への新たな作用解明
・各種ホルモンの心作用
c. 臨床電気生理学的検査(EPS)を用いた臨床研究
・解剖学的見地からみた頻脈性不整脈に対する新たなカテーテル焼灼部位の開発
・EPS解析から各種不整脈に対する新たな抗不整脈薬治療法の開発
d. マイクロニューログラムを用いた交感神経活性の検討
e. 血圧日内変動解析からみた新たな降圧治療法の開発
f. 睡眠時無呼吸症候群に対する臨床的研究 内分泌代謝グループの研究テーマ
a. 自己免疫性疾患の発症機序解明
・抗原提示機構の解明(ユビキチン/プロテアソーム系の関与)
甲状腺自己抗原
I型糖尿病における自己抗原
・バセドウ病眼症における新たな自己抗体の発見と眼症発症との関連
b. 癌特異的抗原遺伝子同定を利用した免疫療法の開発
c. 甲状腺未分化癌に対する新規抗癌剤創薬(プロテアソーム活性制御の面から)
d. 電気生理学的観点からみた甲状腺細胞機能(イオンチャネル機構)
e. 炎症性甲状腺中毒症の病態解明
f. 長期臨床経過からみた萎縮性甲状腺機能低下症発症機序解明
g. 甲状腺機能と心血管系異常
h. 膵、腸管、骨格筋の潅流実験を用いた研究
i. 糖尿病性自律神経障害の病態解明
j. 糖尿病性腎症進展阻止に関する研究 機能再生医科学専攻再生医療学分野との連携
心血管系再生医療の展開をめざして
a. 心筋細胞膜チャネル蛋白安定化(既存ないし新規薬物を用いた)による不整脈治療(ユビキチン/プロテアソームによる蛋白制御)
b. マウスES細胞を用いた心筋細胞への分化
・バイオペースメーカー開発
・心不全治療への応用
c. 冠動脈血管再生治療をめざした研究
膵β細胞の再生治療に向けた研究の展開(遺伝子機能工学との連携:予定) 各種膠原病の血管炎による指趾壊疽に対する血管再生療法開 医工学連携による研究の展開
プロテオミクス研究からのチャンネル安定化による心房細動のテーラーメイド治療の開発;医工学連携プロジェクトを用いて 数理モデル化チャンネル遺伝子導入によるES細胞からの生物学的ペースメーカーの開発;医工学連携による非線形力学的解析を基盤として 医工学連携による甲状腺未分化癌に対する新規抗癌剤創薬に関する研究
戀戻る